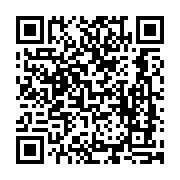ABOUT ご依頼に際してのお願い
- YouTubeで発信しているスタイルに共感して頂ける人が最高のお客さんです。是非ともご依頼前にご覧ください。
- ご予約優先のため、事前にご来店前にご連絡ください。いきなりご来店された場合は担当不在のため対応が出来なかったり、塩対応となる場合がございます。
- 作業が早いことや、ご請求金額の安さだけを求めている人は当店では提供が難しいためご遠慮ください。
- 公道を走行する車両においては保安基準に適合した公認車両であること、又は保安基準に適合するための修理での御入庫のみお受けしています。
SERVICE 事業内容
クルマ/バイク(国産車・外車・レーサー・クラシックカーなど)の
- 故障診断/修理/車検/点検/チューニング/カスタム 整備事業
- 中古車/新車 販売事業
- 各種オイル/オイル添加剤 用品販売事業

レースシミュレーターによる
- 車両販売相談事業
- 体験走行/トレーニング事業
- 導入活用コンサルティング業
ロードサービス
事業
事業
レンタカー/レンタルバイク事業
RESERVE ご予約・作業依頼方法
営業カレンダーを確認して頂き、ご希望の日程をお問い合せ方法をご覧いただきご連絡ください。
折り返しご連絡させて頂きます。
折り返しご連絡させて頂きます。
CONTACT お問い合わせ方法
1
公式LINEからお問い合わせ
一番素早く確実な対応が可能です!
- ※LINEアプリがインストールされた端末が必要になります。
2
メールでお問い合わせ
LINEが使えない方はご利用ください。
- ※迷惑メールフォルダに入ってしまったり、件数が多いため見落とす可能性があります。
折り返しの返信が無い場合は再度お問合せください。
3
お電話でお問い合わせ
緊急時を除き、お急ぎでない場合はご遠慮ください。
- ※見積りや作業内容についてのご質問にはお電話ではお答えしません。
- ※作業中や接客中は折り返しのご連絡となります。
TEl.0877-98-1893
- 営業時間10:00~19:00
- 作業受付可能時間18:00まで
- 定休日日・祝 その他営業カレンダーに準拠
自転車の問い合わせはこちら
TEL.0877-98-2067
受付時間10:00~18:00(日・祝を除く)